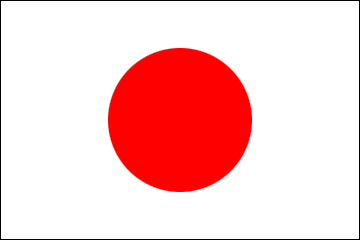新型インフルエンザ情報 - 在ボストン日本国総領事館
新型インフルエンザ情報
鳥・新型インフルエンザに関する当館主催講演会の報告 (2007)
12月1日(土)、ボストン日本語学校において、当総領事館主催によるインフルエンザ講習会が開催され、岐阜大学大学院医学研究科小児病態学講師、ハーバード大学分子細胞生物学客員研究員である加藤善一郎氏(小児科医、医学博士)を講師にお招きして、「インフルエンザのABC2007-新型インフルエンザから身を守る 私のために、家族のために、みんなのために-」と題する講演とディスカッションを行いました。
加藤氏には、昨年もボストン日本語学校の保護者の皆様を対象に同様の講演を行って頂きましたが、各参加者から大変ご好評を頂いたことから、今年も冬のインフルエンザ流行時期に合わせて、今回はボストン周辺の全在留邦人に対象を広げて講演をお願いしたものです。
1、講演会概要
加藤講師からの講義
- インフルエンザに関する様々な疑問や予防策について解説いただきました。講演では、冒頭に、非常に当たり前のことではあるが、各家庭における日頃からの「手洗い」「うがい」「日々の体調管理」といった基本的な予防対策を習慣づけることがとても重要であるとの話があり、なぜそうなのかについて、新型インフルエンザウィルスの構造と感染の仕組みについて、コンピューターグラフィックを用いて丁寧かつ分かりやすく説明して頂きました。
全体を通して、「手洗い」「うがい」「日々の体調管理」の3つにより、体内への侵入経路を断ち切り、のど・鼻粘膜での1次増殖を抑えることが、新型、旧型にかかわらず、自分自身を守り、流行(パンデミック)を防ぐ上で、最も大事なことであるということ、さらに上記に加え、「予防接種」が大切である理由などについても解説いただきました。最後に、以下の3つのキーワードにまとめていただきました。
A = always
B = block
C = colonization & cut the pandemic chain
ディスカッション
各参加者から自らの体験や日常生活上での素朴な疑問について活発な質疑が行われ、加藤講師より、予定時間を超過しながらも丁寧なアドバイスがありました。ここにその一部を紹介します。
Q.マスクは着用した方が良いのか?
A.唾液などの飛沫感染を防ぐ効果があるので、着用した方が良い。ただ、マスクをすることで、本来の手洗いやうがいを怠ってしまいがちにならないよう注意が必要である。また、アメリカと日本の習慣上の違いから職場等でのマスク着用には問題が生じることがあり、むしろ、感染蔓延を防ぐ意味では、感染時には外部との接触をできるだけ控え、自宅での療養による体調管理が重要であることを十分認識してほしい。
Q.うがいのタイミング、うがい薬や塩水を使用することはどうか?
A.外出後にうがいを励行してほしい。ウィルス増殖を抑えるという観点から、寝ている間に増殖することを防ぐ意味で、特に就寝前が大切である。通常のうがいでは盲点となっている鼻腔粘膜における「うがい」も考慮すべきである。また、普通の水道水を使用することで十分である。
Q.インフルエンザで子供が高熱を出した時の対処法は?
A.こどもの脱水を防ぐためにも水分補給に注意すべきである。解熱剤だけに頼るのではなく、スポンジ等に水分を含ませて体を濡らし、体温を放出させる方法も有効である。
2.講演会終了後に参加者の方から回収したアンケート結果について
講演内容について、分かりやすかった、参加できて良かったと答えた方が多数でした。一方で、今シーズンのインフルエンザの予防接種の接種状況をみると約半数の方が未接種であることが分かり、今後、予防接種に関する一層の情報提供等の必要性が感じられました。
新型インフルエンザ対策・予防接種情報に関する過去の情報はこちらから
鳥・新型インフルエンザに関する当館主催講演会の報告
2006年12月9日、当館はボストン日本語学校において、岐阜大学大学院医学研究科小児病態学講師、ハーバード大学分子細胞生物学客員研究員である加藤善一郎氏(小児科医、医学博士)を招き、日本語学校生徒の保護者を対象に、「インフルエンザのABC-新型インフルエンザから身を守る-」と題し、鳥・新型インフルエンザに関する講演会を開催いたしました。
右講演会では、加藤講師より、インフルエンザに罹る仕組み、新型インフルエンザウイルスの構造、インフルエンザ予防対策等について講演頂き、新型インフルエンザがなぜ生じてくるのか、新型と従来型との違いはどこにあるのか、ワクチンとはなにか、消毒するということはどういうことなのか、鳥肉を食べていいのか、抗インフルエンザ薬はなぜ効くのか、なぜ医者はインフルエンザに罹らず日々診療を続けられるのか、ウイルスを防ぐ基本など、多岐にわたる疑問について、正しく理解し行動するための方法が紹介され、その後、参加者との活発な質疑応答が行われました。
加藤講師からは、新型インフルエンザへの予防対策としては、通常のインフルエンザを予防するための対策と同様に対応することが重要であり、インフルエンザ予防の基本として下記の3点が重要であるとの話がありました。
予防の基本
- 1、手洗い:食事前に手を洗う(石けんなどの併用がベター)
- 2、うがい:のどだけでなく鼻腔についても行うのが効果的、最低就寝前に1回
- 3、日々の体調管理:自分の体調を把握して、日々の変化に気づく
同講師からは、これらの予防対策は、なんら特別なことではなく、当たり前のことではあるが、毎日欠かさずきちんと実行するには、なぜそれらが有効なのか、自分自身がきちんと理解することが不可欠であるとの考えから、インフルエンザの病態、ウイルスタンパクの立体構造という分子医学的な面からの説明がなされました。
新型インフルエンザに関する勉強会報告
2006年5月25日、当館にて新型インフルエンザ対策に関しまして、ハーバード大学公衆衛生大学院の永田高志先生及び同大学で分子・細胞生物学を専攻する加藤善一郎先生を講師に招き勉強会を行いました。同勉強会で、両先生が述べられた内容につき在留邦人の方々にも役立ててもらうべく次の通り当館ホームページに掲載致します。
近年、鳥インフルエンザを含む新型インフルエンザの世界的大流行の可能性について世界の関心が高まってきている。日本のメディアでも現在、感染流行が確認されている東南アジアの鳥インフルエンザの状況やWHO(世界保健機構)の報告がしばしば取り上げられている。2006年6月20日時点でH5N1型鳥インフルエンザの感染者は228名、うち130名が死亡しており、致死率は50%以上と非常に高率である。米国の公衆衛生関係者の間でも新型インフルエンザ対策は最優先事項の一つとして考えられ、一般市民の関心も高い。2006年5月時点での米国全体及びマサチューセッツ州における新型インフルエンザのパンデミックに対する取り組み及び一般市民として出来ることに関し次の通りレポートする。
1.マサチューセッツ州の新型インフルエンザ対策
米国の災害における実際の行政対応は原則として州単位または地域単位で行われる。つまり具体的な災害対策は州または地域の対応能力に大きく依存するといえる。ミット・ロムニー・マサチューセッツ州知事は2006年2月7日に新型インフルエンザに対する行動計画を発表した。災害の対応計画を練る段階において、過去の事例に基づいた想定を考え、それに基づいて行動計画を立案するのが一般である。今回は1918年のスペイン風邪のマサチューセッツ州での大流行(全住民の約30%が罹患)および1957年および1968年の米国におけるインフルエンザの大流行(全住民の約30%が罹患)の際のデータを元に想定を作成した。概要は次の通りである。
マサチューセッツ州保健局における新型インフルエンザのパンデミック想定
(1)マサチューセッツ州全体における患者想定
- 住民全体650万人の30%、200万人が感染する。
- 感染者のうち4%、8万人が入院する。
- 感染者のうち1%、2万人が死亡する。
- パンデミックの期間は約8週間。
(2)医療機関における患者想定
- 集中治療室での入院を必要としない感染者の平均入院日数 5日間。
- 集中治療室での入院を必要としない感染者の平均入院日数 10日間。
- 人工呼吸器の装着期間 10日間。
- 集中治療室での入院が必要な患者 約50%。
- 入院患者の死亡率 70%。
- 患者の増加率 一日当たり3%。
(3)病院の患者受け入れ想定
- 定例手術等はキャンセル。
- 緊急性を要しない患者は亜急性期のための医療機関、ないしは自宅へ転送。
- 投入可能なすべての病院ベッド、スタッフ、資機材、ボランティアを用いる。
- 病院は集中治療室の場となる。
- 関係者の努力にもかかわらず、病院には対応不可能な数の患者が押し寄せてしまう。
- 病院の機能は60%まで低下する中で(スタッフの40%が出勤拒否)、病院の機能停止を防ぐ。
- 病院内にインフルエンザユニットを設立。
- 病院外にインフルエンザのトリアージセンターなどの臨時診療所を設立し、入院が必要な患者のみ転送。これは病院にインフルエンザ患者が集中することを避けることを目的としている。
このマサチューセッツ州の新型インフルエンザ対策の特徴は次の通りである。
(1)医療資源の有効活用
マサチューセッツ州政府は、州全体を6つの地域に大別し、その各エリアの中で対応することが決められた。具体的な対応はまず各エリアで行い、許容能力が超えた場合は州レベルで対応、さらにそれでも困難であれば、連邦政府の応援を求めることは合意事項となっている。そして各6地域の医療機関においてどれだけ病院のベッドを保有しているか、そしてパンデミックの際にどれだけベッドを稼働できるかを把握している。現時点では、想定のパンデミックに対応するだけのベッドは辛うじて確保されていると算出された(パンデミックの際に必要とされるベッド数はマサチューセッツ州全体で2万3,560床、それに対して現時点で確保可能な病床は2万4,024床)。これらの病床は4段階に区別されている。レベル1は対応する医療従事者がいて即応可能な病床、レベル2は現在入院中の患者の退院や転送、ルーチン業務の延期などで利用可能な病床、レベル3は認可済みだがスタッフの手配がなされていない病床、そしてレベル4は通常は病床として設置されていないが緊急時に病院の体育館や食堂を利用して増設される病床である。レベル1、2、3までは酸素の配管など設備が整っていることが条件である。その比率は64%、15%、21%である。単なるベッド数のカウントだけでなく、機能評価を行い状況に応じて病床を柔軟に運用できるような体制がすでに構築されている。
同時に必要とされる人工呼吸器、薬剤、その他医療資機材についても検討されている。パンデミックの際、医療機関にはマスクや防護服などの各種医療資材が必要となるが、州政府でストックを管理し、必要に応じて補充することになっている。
(2)災害訓練
マサチューセッツ総合病院では05年10月の時点で救急室にて新型インフルエンザの流行を想定した災害訓練が行われ、患者対応の難しさ、医療スタッフの確保などさまざまな問題点が浮かび上がり、それをもとに体制の強化に努めている。また米国保健省も机上訓練のシナリオを一般公開し、医療・公衆衛生関係者に各種訓練を行うことを奨励している。
2.一般市民として出来ること
当局でも色々な対策を考えているが、まず実際に米国でパンデミック(大流行)が発生した場合、重要なことはそれへの対応については地元の医療機関、危機管理体制に注意すること。パンデミックの際、直接的な人的被害以上に、風評による混乱が予想されるが、これを防ぐ為にはラジオ、テレビや米国政府(CDC、保健省、FEMA)やWHOのウエブサイトなどを通じた適切な情報の入手、把握が重要となる。また、パンデミックになった場合には、保健当局から流行を防ぐ為に混雑する場所を避け、仕事にも出ないで家にいるように指導されることが予想されるが、そうした中でも友人や近隣者と連絡を取り、備蓄食糧がなくなった場合には共有できるようにするなど準備することが重要である。現時点で、一般市民が出来る対策としては次の点が挙げられる。
- 手洗い(子供への教育を含む)。
- 公共の物を触った後は抗菌剤入りの手洗い洗剤を使う。
- 体調が悪い時は自宅待機。
- 咳をする時は口を押さえる。
- 咳や鼻水を持つ人からは3フィート(約1メートル)離れる。
- 適応があれば定例のインフルエンザワクチンを受ける。
- 本人、家族への教育
- (イ)新型インフルエンザに関する米国連邦政府公式ホームページ (www.pandemicflu.gov))を読む。
- (ロ)可能な限り保存食を蓄える。
- (ハ)かかりつけの医療機関に頼んで30日分の薬剤を予め買う。
- (ニ)体調を整え、規則正しい生活を送る。
3.米国連邦政府の新型インフルエンザ対策
2005年夏のハリケーンカトリーナに対する対応の失敗に対しブッシュ政権への批判の声が高まる同年11月1日に、ブッシュ大統領は米国における新型インフルエンザ対策計画を発表した。この中で(1)米国への感染の拡大を抑止、遅延、または限定させる、(2)社会インフラを維持し被害の減少に努める──ことを目標設定している。各種対策のために71億ドルの新規の予算が計上され、うち38億ドルが翌月12月に議会の承認を経た。予算の75%はワクチン開発とタミフルなどの薬剤の購入に当てられている。さらに06年5月3日には新型インフルエンザ対策のための実行計画を発表した。その中で政府機関を中心に300項目にわたる行動計画を明記している。新型インフルエンザに対する連邦政府の対応は国家安全保障省を中心としたものであり、単なる感染症ではなく国家安全保障上の問題として位置付けられているのが特徴である。
米国の新型インフルエンザ対策は大局的に見ると、2001年より推進してきたバイオテロ対策で構築したシステムをインフルエンザ対策に転換する形をとっている。ニューヨークの世界貿易センターおよびワシントンDCのペンタゴンに旅客機を用いたテロが行われた直後の01年10月に「白い粉」の形状をした炭疽菌が郵便物を通じてテロとして用いられ、翌11月末の段階で感染確定者19名、うち死者5名が発生した。これに対応するべく、米国の公衆衛生部門はバイオテロ対策を積極的に推進した。バイオテロ対策で必要とされたシステムは、(1)サベーランスシステム、(2)病原体同定の検査体制の確立、(3)大量の傷病者が発生したときの医療機関の受け入れ態勢、(4)ワクチン開発、(5)薬剤の配布システム、(6)隔離、(7)リスクコミニケーション──である。インフルエンザ対策では、これらにWHOを中心とした国際的なネットワークの確立が加わることで、新型インフルエンザ対策の骨格が確立された。
米国の優れている点に抗ウイルス薬のタミフルやワクチンなどを戦略物質として位置付け、国家備蓄(National Stockpile)しており、有事の際は短時間で全米各地に展開できることが挙げられる。2006年12月までに全米2,600万人分の治療に必要なタミフルのストックを確保できるように準備が進められている。そして各病院でもストックが確保されているが、保管場所や方法については機密事項となっている。ワクチンについては、現時点でヒトへの臨床使用が可能なH5N1インフルエンザウイルス用ワクチンは開発されておらず、畜産用のワクチンのみが存在しており、この畜産用のワクチン400万人分がストックされている。
(なお、この報告の作成に際しては永田高志先生が医療雑誌「連携医療 2006 Jul.」に掲載された論文「『パンデミック=災害』との認識で対応する米国 新型インフルエンザの蔓延に無防備な日本」を参考にさせて頂きました。)
参考資料
- 新型インフルエンザに関する米国連邦政府公式ホームページ
http://pandemicflu.gov/ - マサチューセッツ州保健局が医療機関に向けて発表した声明 http://www.mhalink.org/public/Disaster/advisories/2006/prep-2006-01-1.pdf
- 外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars.asp
鳥インフルエンザの注意事項
1.鳥インフルエンザの現状
(1)新型インフルエンザ発生への引き金となる事が懸念されている鳥インフルエンザは、アジア・中国・ロシア・ヨーロッパ、さらにアフリカに広がり始めています。
(2)鳥インフルエンザは鳥類の伝染病ですが、感染した鳥(感染して発症している鳥や感染した結果死んだ鳥)と近距離で接することによりヒトへの感染が起こる場合があります。また、ウイルスは生きた鳥の糞の中にも大量に存在しますが、鳥の種類によっては感染しても無症状でありながらウィルスを排出するものもあり、現在の鳥インフルエンザ流行の要因の一つとなっている可能性があります。
(3)現段階では鳥インフルエンザのヒトへの感染は一般的でなく、ヒトへの感染のほとんどは発症している鳥との直接接触(鳥を殺す、羽をむしる、料理の準備など)によるものです。しかし、鳥インフルエンザ・ウイルスの感染地域の拡大は、ヒトへの感染の機会が増えることにつながり、ヒトへの感染症例が増えることによってウイルスの感染力が増し、ヒトからヒトへの感染が容易となるウイルスが出現する可能性が高くなることから、WHOでは引き続き警戒を強めています。
2.感染予防対策
*鳥インフルエンザの家禽類及びヒトへの感染が確認された地域への渡航、滞在を予定されている方は、安全を確保するために引き続き以下のことを念頭において行動するようおすすめします。
- (1)手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。(手洗いは石鹸を泡立てて流水でしっかり洗うこと)
- (2)鳥インフルエンザの流行が見られる地域の鶏舎やアヒルなどの鳥を放し飼いにしている場所に近づかないこと。
- (3)鳥インフルエンザの流行が見られる地域において、生きた鳥への接触、また、生きた鳥を扱う市場へは、不用意・無警戒に立ち寄らないこと。
なお、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などインフルエンザと同様の症状が現れた場合は早めに医療機関において受診するようにしてください。
*マサチューセッツ州政府公衆衛生局はインフルエンザ及び鳥インフルエンザ予防のために次の事を行うよう呼びかけています。
- (1)インフルエンザ感染経路となる目、鼻、口に触れないようにする。
- (2)咳やくしゃみをする時には口をティシュペーパーや服の袖で覆う。
- (3)扉や冷蔵庫の取手等職場等で頻繁に触れられる場所を清潔にする。
- (4)風邪やインフルエンザなど病気にかかっている人との至近距離での接触(抱擁、キス等)を避ける。
- (5)子供や免疫力が弱い人は人混みに入ることを出来るだけ避ける。
- (6)インフルエンザの兆候がある場合は、自宅で休養する。(大人の場合は最低5日間、子供の場合は7日間)
- (7)毎年インフルエンザ予防接種を受ける。
- (8)肺炎の恐れがある人は医師と相談した上で肺炎球菌ワクチンを受ける。
3.WHO発表及び勧告その他の関連情報は以下のホームページに掲載されていますので、そちらもご覧ください。
- WHOホームページ:http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
- 感染症情報センターホームページ(WHO情報を和訳したものを掲載):http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
- 厚生労働省検疫所ホームページ:http://www.forth.go.jp/
4.MA州公衆衛生局及び疫病管理センターのホームページは以下の通り
- http://www.mass.gov/dph/flu
- http://www.cdc.gov/flu/
- マサチューセッツ予防接種プログラムの電話は617-983-6800又は888-658-2850
5.東南アジア地域への旅行者の方へ
問い合わせ先
外務省領事局政策課(医療情報)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
外務省 海外安全ホームページ:
https://www.mofa.go.jp/anzen/
在ボストン総領事館:
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/index.html
電話:617-973-9772