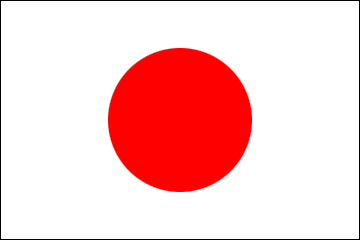研究者のためのキャリアセミナー(2018年4月8日)の開催報告掲載
2018年4月18日(日)午後2時~4時までマサチューセッツ工科大学(MIT)において、日本人若手研究者の米国でのキャリア構築の一助とするためのキャリアセミナーを開催しました。 冒頭の道井総領事の挨拶のあと、約100名の参加のもと、当地ボストンで活躍する日本人研究者5名のパネリストが経験談や後輩への助言を語り、聴衆からの質問に答えるパネル・ディスカッション形式で積極的な議論が行われました。
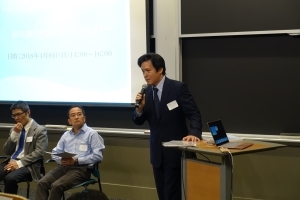
道井総領事挨拶

パネル・ディスカッションの様子

森井政宏 教授
Professor of Physics, Harvard University

内田直滋 教授
Professor of Molecular and Cellular Biology, Department of Molecular and Cellular Biology, Harvard University

長谷川耕平 准教授
Associate Professor of Emergency Medicine, Harvard Medical School
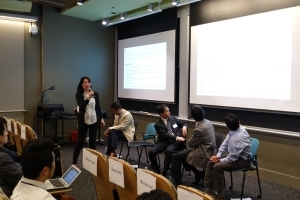
西原玲子 助教
Assistant Professor of Pathology, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School

荻野周史 教授
Chief of Program in MPE Molecular Pathological Epidemiology, Brigham and Women’s Hospital (BWH);
Professor of Pathology, BWH, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School;
Professor (Epidemiology), Harvard T. H. Chan School of Public Health;
Associate Member, Broad Institute of MIT and Harvard、
ボストン日本人研究者交流会(BJRF)アドバイザー
*敬称略
- 米国で研究活動をする上での英語の重要性
- 日本の英語教育は冷め切った鉄を打ち込んでいるようなもので意味がない。自分も英語力の面で米国での就職活動・研究費(グラント)取得等に不利に働き大変な思いをした。日本の公用語に英語を加えるくらいの改革が必要。また普段からメールも会話も全部英語にするべきである。自分が渡米した際には周りに日本人がほとんどおらず、数年間日本語を用いなかった。(荻野)
- 発音が良い方がよいのは確かだが、それ以上に大切なのは、英語が下手でも堂々と大声で話したり、反対意見であっても自分の意見を主張する根性である。教授に対する反対意見を堂々と述べても米国では全く問題ない。議論をするためには自分がしっかりと考えて意見を持つ必要がある。(森井)
- 発言に内容があると、たとえ発音が完璧でなくても話に耳を傾けてもらえるので、話を聞くに値する人であるという信用を構築していくことも大切。グラント申請については、たとえネイティブでも書き方が上手くない人もいる。ライティングについては、数をこなし、上手い人の文章構成等から学んで改善することができる。(長谷川)
- 留学して初めのころはアウトサイダーで議論の場で発言できなかったので、少し間が空いて質問する人がいない場合などに意識して最初に質問するように努力した。また、ライティングについてはプロの人に指導を受けたのが効果的だった。(西原)
- 堂々と話すための度胸を持ってほしい。日本人はプレゼンテーションの力が弱いと思う。アメリカ人は学部生でも立派なプレゼンテーションをする。研究発表する際はすべてジョブ・トーク(就職活動の際のプレゼン)であり、将来の道を切り開くきっかけになると考えて、毎回きちんと準備をすることが大切である。また、グラントや論文のライティングについては、他人の論文を当事者として読み、構成等について勉強することで上手な書き方を学んで英語力を補うことができる。発音についてはトレーニングであり、車の中で英語の歌を聞きながら発音練習するなど時間を見つけて行うことも役に立った。(内田)
- キャリア構築の際に大変だったこと・良かったこと
- 研究者としてはリスクをとらないことがリスクになる。自分の研究分野だけでなく、科学全体が時代と共にどう移り変わるのかという視点で自分の研究の価値を考えて、積極的に面白い分野、新しい場所に行ってみることが大切である。自分自身のキャリアを振り返っても、病理学、薬理学、統計学を学び、現在は分子病理疫学という新たな統合分野を立ち上げ常に新しい研究を行ってきた。(荻野)
- グラントの取得に大変苦労している。国立衛生研究所(NIH)の一般的なグラントのRO1の採択率は10%であると言われている。そんな中、確立したキャリアを持った教授等と争って、分野を変えるイノベーションを起こせることを証明しなければならないため大変である。(西原)
- グラントについては、取れるまで何回でも出すことが重要である。また、皆が申請しないようなユニークなグラントを探して出願したり、大きいカテゴリを細分化して再出願するなど、色々と工夫している。(荻野)
- 研究室を持って独立したころ、NIHのグラント申請に10回ほど落ちたが、英語でグラント申請する練習になり、失敗から学ぶことができたのでかえって良かったと思っている。グラント申請は失敗してもともとであるので、どんどん申請して何かを得ることが重要だと思う。(内田)
- 自分はキャリア形成で大変だと思ったことはなく、何でもポジティブにやっている。自分の研究室の教授と同じような研究をしても勝ち目がないので、違う研究をしてWin-Winの関係を築き、自分の存在が研究室全体にとってのベネフィットになるようなるように心がけたこと、ここ3-4年の研究室のグラント申請を全部自分で書いたことで研究室の方向性が自分にとって良い方向に向かっていったことが振り返れば良かったことである。(長谷川)
- 自分が最もリスクをとったのは、東大をやめてスタンフォード大学に移った時である。新しい場所に移り、信用を一から築いていくことは大変であったが、2年ほどで手に職がつき、さらに2年ほど在籍したあと結婚し、職探しの結果ハーバードに移籍することになり、誰も教えたがらない講義を担当して、大学で教えた経験もないのに講義のやり方について一から勉強することになった。振り返ると、2~3年ごとに新しい環境に移り、居心地が良くなったらやめるほうが、自分自身の成長につながったと思う。また、その際は意外なことが役に立ったので何でも経験をしたほうが良いと思う。例えば、大学の講義を始めて担当した際には学生のアルバイトで塾講師をした経験が役に立った。(森井)
- メンターを多く持つことが大切だと思う。最初に米国に来た際の研究室の教授には、24時間の80%は研究をしなければならないと言われて勉強になった。また、特にボストンには専門性を持った一流研究者が多数いるので、面白いコラボレーションを行うことができる。(西原)
- メンターはたくさんいる。また、自分と直接関係のない人でも積極的にアプローチしてネットワーキングすることでメンターは勝手に増やせるし、コラボレーションも可能。(荻野)
- 研究自体については大変だったと思ったことはあまりない。将来のことを心配しすぎず今の研究に没頭することが大切だと思う。キャリア構築には人とのつながりが役にたった。現在の職に就くまで、約20カ所に応募し、面接に呼ばれたのが3カ所でオファーを受けたのがハーバードであった。思えば、採用のきっかけになったのがハーバードに留学している友人の紹介によりハーバードでセミナーをして教授と知り合いになり、個人的なつながりを作ったことである。当時は珍しかった電気生理と行動実験の組み合わせに興味を持ってもらえたことが採用につながった。運が重なったともいえるが、当時から実験成果が出るたびに、機会があれば色々なところで積極的に発表するように心がけていた。日本に帰ったときも同様に、知り合いにお願いしてセミナーをさせてもらうなど発表の機会を設ける努力をするべきである。(内田)
- 自分も当時研修を行ったペンシルバニアで仕事のオファーを得られなかったため、全米の50近くある施設に履歴書を送り面接に呼ばれたのがハーバードだった。応募して不採用になるのは当たり前であるので、めげずに応募することが大切である。(荻野)
- 博士研究員(ポスドク)・助教を採用する際に重視すること
- 自分にない専門性を持っていることである。(荻野)
- ポスドクに関しては物理学に対してセンスのあり、自分よりも大物になれそうな学生を選ぶようにしている。助教に関しては完全に独立した研究者(PI)であるので、自分の研究とオーバーラップがなく独自性のある研究者を選ぶ。(森井)
- 助教に関しては部下というより同僚であるので、自分と対等に議論ができる人を求める。日本人にはポスドクでよい仕事をしたにも関わらず、助教の仕事が取れない人が多いと思う。発表だけでなく、発表後のチョーク・トーク(雑談)が上手くないところで差があることが一因ではないか。チョーク・トークでは自分の研究への深い理解や、分野を見渡す広い視野などが自然とわかってしまうためである。力をつけるためには、周りの優秀な同僚と議論を行うべきであるし、教授に意見することがあっても米国では全く問題がない。近年議論を挑んでくるポスドクが減ったように感じる。(内田)
- 結婚や出産等のライフイベントとキャリアの両立について
-
- 出産後にどうやって家庭と仕事の両立を行っていくかについて、周りに同じような境遇の人がいないためどうしたらいいか試行錯誤した。いろいろなイベントに出かけたり、ロール・モデルに話を聞いたりしたが、皆それぞれ事情はあっても苦労を表に出さない人が多くてなかなか情報を集めることができなかった。家事については苦手なことをオートメーション化して省くなど工夫をしている。(西原)
- 妻も物理学者であり、ポスドクの終わりに結婚してハーバードに移ってからも二人とも研究を続けていた。誰かの助けがないと生活を回していけないので住み込みのお手伝いさんを10年間雇った。やはり子育て等は母親にかかる負担が大きいと思う。(森井)
- 米国で活躍している日本人が減るなど国際競争力の低下が懸念されるが、日本はこれからどのようにしていけばよいか
- 少子高齢化・人口減少の時代に突入していく中で50年後に日本はどうありたいかとういうビジョンがまず必要だと思う。(長谷川)
- 国際競争力をつけるための英語の公用語化が必要。社会に多様性がなく、社会のトップ層が男性ばかりである点も改善するべきと思う。もっと日本が多様な考え方や意見を取り入れられるような社会に変わっていくべき。自分自身は日本の大学院に進んで日本の研究環境が嫌になったので、退路を断って米国で医師になる道を選んだ。米国でキャリアを構築するのは大変だったが、今は大学院で日本を飛び出して良かったと思っている。(荻野)
- 米国では大学院博士課程に入学すれば給与をもらいながら研究ができるといいった事実が若者にあまり知られていない。今は普通の大学生が考慮に入れる選択肢ではないと思う。早い時期から米国へ留学して日本国内に限られない多様な選択肢が広がることがもっと知られればよいと思う。(森井)
- 身近に海外留学している人がいるなど、海外でのキャリアパスを実際に見られるが大切ではないか。そのために留学している皆さんが日本に帰国して留学の魅力を伝えてほしい。自分の場合は出身研究室の教授が同じ研究をすることは禁止されており、ほとんどの人が留学する研究室だったため留学が身近だった。また、日本には制度上の問題もある。日本では大学院の授業料等を自分で納める必要があり、自分自身も学生時代はアルバイトをしていた。これは学業に集中できない本末転倒な話であり、国力を弱める結果につながっていると思う。米国では大学院生は給与をもらいながら必死に勉強をする。米国はこうしたサポートを国の将来に対する投資だと思っている点が違う。(内田)
- 日本人の中には、米国の大学院に留学して日本を離れる期間が長いほど日本とのコネクションが薄まってしまいリスクになると考える人もいると思う。これは、日本のアカデミアが外国でトレーニング等を受けた人材の受け入れにあまり積極的でないことも一因だと思う。(西原)
- 日本では教員のほとんどが同じ出身大学であるというケースも未だにあるが、米国の一流大学のほとんどは内部人材以外の多様な人材をリクルートして組織力を高めている。(荻野)
- 面白いことに挑戦して失敗することはやりがいがある。もちろん、パネリストになる人はリスクをとって成功した人であるため、失敗する人もいることを頭に入れておかなければいけないが、米国で博士号をとって日本に帰って本当に生活に困った人を聞いたことがない。先のことを心配しすぎる必要はない。(森井)
- 留学する際に出身研究室の教授に「日本には帰るところはないと思え」という言葉をかけてもらったことがとても良かったと思っている。教授は自分の研究室出身の人は引き入れないという考えの人であった。この言葉で留学するにあたって気を引き締めて仕事に取り組むことができた。日本にコネクションを残したまま仕事をするよりも、目の前の研究に全力を出して成果を出すことの方が重要である。(内田)
- 研究の継続性は意識しているか
- 自分は研究分野を時代に合わせて変えており、その分野が拡大していくか縮小していくかを常に考えている。そのために自分の研究分野に限られない科学全体の流れを常に意識し、生物学の中で何が大切かを考えている。例えば、がん研究で免疫療法と言えば今は最も注目されているが、10年前には今ほどの注目度はなかった。しかし自分はがん細胞が免疫細胞に囲まれているという生物学的事実を考えた上でこの分野が伸びることを予想して、早い段階からこの分野に着目することができた。(荻野)
- 博士課程の研究とその後の研究が同じ分野である必要はない。むしろ、分野を変え経験を積んで懐が広げることは評価に値するものである。そのためには自分の研究を行いつつも幅広い分野の論文を読んで何が面白いのかを考えていくことがよい。(森井)
- 日本と米国で研究の流行に違いはあるか
- 米国と日本のシステムの違いがある。日本では若手が研究を始める際にもらえる研究費が多くて数千万円と少額である。一方で米国では若手でもスタート時に多額の研究費がもらえるので、それに見合っただけの全く新しい研究を行うことが期待される。その結果、米国では流行を追う傾向が出やすいことが考えられる。また、NIHの研究費には間接経費という若手の人件費等に使える経費があるため、研究費が次の世代につながるシステムになっている。(内田)
- 日本では前世代からの研究の継続性は意識されやすいと思う。米国では独立して研究室を持つからにはそれまでにない革新的な研究を行うことが期待される。(森井)
- 経歴の重ね方・アピール方法について
- 大学院博士課程とポスドクの研究テーマが違うことは当たり前である。むしろ違う研究室でそれぞれきちんと仕事をしていることは、研究室のトップではなくその人個人の実力の証明にもなり評価に値する。(内田)
- 同じことを同じ研究室でずっと継続してきた人は米国ではむしろ冒険心がないとみなされる危険がある。日本では同じ大学にずっと在籍し、それをよしとされる傾向にあると思う。教員の募集になると同じポストに何百人もの応募があるケースもあり、その中で如何に独自性や専門性があり他の人と違うかをアピールできるかが重要である。(荻野)
- 研究室を運営するにあたっての指導方法
- 以前は違ったが、現在は基本的に放任主義である。逆に言うと、自分の研究室のメンバーには自分のキャリアは自分で作るという気持ちを持ってもらいたいと思っている。(荻野)
- PIになりたての頃は指導方法がよくわからず自分で手を動かして実験していたこともあったが、最近はやめた。同じデータでも解析方法が違うと結果が異なるので、その点について議論をして適切なアドバイスを行い、研究を発展させていけるように指導している。(内田)
- 物理学では生物学よりチームが小さいので、直接コミュニケーションができるが、今は日々進化しているプログラミングは任せて物作りには参加するようなスタイルにしている。(森井)
以上