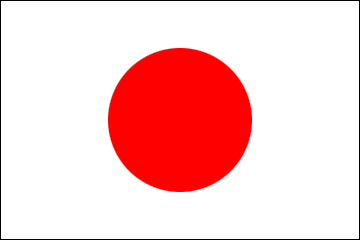ニューイングランドで活躍する日本人研究者紹介 (MITメディアラボ 佐野あかねさん)
1. 研究テーマについてお聞かせください。
マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボのAffective Computingグループに所属し、リサーチ・サイエンティストとしてウエアラブルディバイスを用いたメンタルヘルスの研究を行っています。ウエアラブルディバイスを用いることで、従来は研究室の測定装置でしか行えなかったストレス計測を日常生活のなかでモニタリングを行い、メンタルヘルス(ストレス・睡眠・うつ病)についての客観的なデータを計測してその意味を理解する研究を行っています。
例えば、「SNAPSHOT Study」という研究では、MITの学部生数百人からウエアラブルディバイスによりデータを収集し、彼らの行動、生体情報とストレスとの関係を分析しました。これにより皮膚から出る微量の汗や体温などの生理学的な反応および携帯電話の使用量、あるいは睡眠のパターンからストレスを推定したり予測することが可能であることが明らかになりました。メンタルヘルスを選んだ理由は近年社会問題となり解決が求められている一方で従来の方法では理解も測定も難しい分野であることです。またMITでは近年学生のメンタルヘルス悪化が問題となっており、如何に学生のメンタルヘルスを維持するかには大学も関心を持っています。
2.米国で研究を始められた経緯についてお聞かせください。
ソニー株式会社でウエアラブルディバイスの研究開発をしており、2010年にソニーを休職(その後退職)してMITメディアラボの博士課程に留学し、Affective Computingグループで去年博士号を取得しました。現在は同じグループで研究を続けています。 会社を退職することは大きな決断でしたが、博士号取得後には様々なチャンスがあることを知り、あまり迷うことなく決断することができました。企業での研究開発は利益の追求という目的がありどうしても制限があります。一方メディアラボではデバイスを用いて得られる日常生活でのデータの理解という自分の興味を自由に追求できるところに魅力を感じました。また、退職後にソニーがメディアラボのスポンサーになったので(注:メディアラボは企業のスポンサー制度により研究が行われている)今でもソニーの人たちとはつながりを持っています。
3.メディアラボでの研究生活についてお聞かせください。
メディアラボは様々なバックグラウンドやスキルを持った人たちが集まり自分の好きな研究を行えるとてもユニークな場所だと思います。研究室ごとに区切られたスペースではなく色々な研究室が1つのフロアを共有しており、他のグループのメンバーとコラボレーションしたり、一人の学生が同時に何個ものプロジェクトに関与したりすることも簡単です。また困った時には色々な分野の人がいるのですぐに相談できます。このような“Antidisciplinary”(脱専門性)は伊藤穰一所長が推進しているメディアラボの象徴的な考え方です。また、Affective Computingグループのピカード教授は非常に協力的で、リサーチプロジェクトは個人に任されており、自分の興味を自由に追求して研究の幅を広げていくことも可能です。
また、卒業後は起業・研究を続ける・アップルやグーグルなどの大きな会社に就職するなど色々な選択肢がある点も魅力です。メディアラボには多くのスポンサーがいてラボの研究成果を利用することができるため、スポンサーと協力することで研究の事業化も可能です。またMITやボストン地域では起業コンペが盛んに行われるなど個人で起業するのにもとても良い環境が整っています。 大変だった点はもともと寡黙な性格なので、他人に自分の意見を英語で伝えることです。留学してからは自分の研究成果のプレゼンや議論に苦労しましたが、2年経つとこれらに自信を持つことができるようになりました。
4.日本での研究生活との違いがあればお聞かせください。
アカデミアについては日本では一般的に研究室ごとの垣根があり、研究テーマを1つに絞らなければならない点がメディアラボとは大きく違うと思います。また、企業では自分の興味を自由に追求することが難しく、その点で現在のメディアラボでの研究環境は気に入っています。
5. ご自身の研究の将来展望や夢についてお聞かせください。
将来的には、自分の研究成果(シード)を基にサービスができて人々のメンタルヘルス、健康、能力向上に貢献することができればいいと思います。ただし、自分でビジネスを行うのではなく、私自身は人と、人を取り巻く環境、社会に関するデータを取り集めて理解する研究を続けて行くことが出来ればいいなと考えています。
6. これから留学を考えている研究者にアドバイスがあればお聞かせください。
日本はとても居心地のよい社会なので日本にいるとそれが世界の全てというような気持ちになってしまいます。しかし一度海外経験をすると、もっと広い世界がありそこには様々な機会があることがわかります。ただし、言語のハンディのなかで自分を表現するための基本的なスキルを習得するには時間がかかるため、数年研究して日本に帰る一般的なポスドクの研究者は苦労をして慣れる頃には帰国するということになりかねません。もし米国で長くやっていきたいと考えるのならば、博士号をこちらで習得することを考えてみても良いと思います。博士課程の在籍中にプレゼンやディスカッション、研究資金を獲得するスキル、あるいは多様性の中で生活をするスキルを身につけることもでき、夏休みのインターンで色々な企業の仕事を体験することもできます。また、OPT制度によりビザの延長ができるため、米国で仕事を見つける際に助けになると思います。
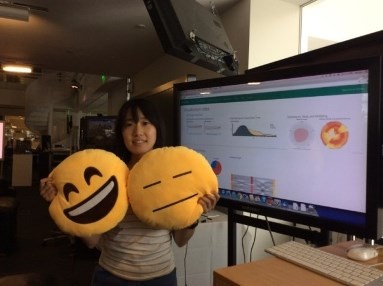

| 2003年 | 慶應義塾大学理工学部卒業 |
| 2005年 | 同大学院理工学研究科修士課程修了 |
| 2005~11年 | ソニー株式会社 |
| 2010年~ | マサチューセッツ工科大学 メディアラボ アフェクティブコンピューティンググループ |
| 2015年10月 | 同大学 メディアラボ 博士課程修了 |
| 2015年11月~ | アフェクティブコンピューティンググループ リサーチ・サイエンティスト |
ホームページ:http://web.media.mit.edu/~akanes/
SNAPSHOT Study: http://snapshot.media.mit.edu/