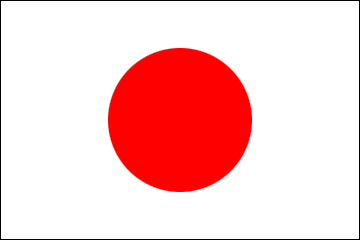ニューイングランドで活躍する日本人研究者紹介 :ボストン大学医学部教授 池津庸哉先生

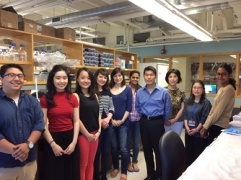
1.ご専門内容についてお聞かせください。
主にアルツハイマー病の研究をしております。アルツハイマー病の患者数は米国では530万人に上り、最も頻度の高い認知症です。オバマ政権はアルツハイマー病を2025年までに治療するためのNational Alzheimer’s Project Actに2011年に署名しました。これによりアルツハイマー病の研究は目覚ましく発展することが期待されています。
当研究室では主に病原性タンパク質の一つであるタウ蛋白がどのように病的に変性し、それがどう脳内で病理像を拡大するかを研究しています。具体的には細胞外に放出される微小な小胞(エキソソーム)がタウ蛋白を包埋し、細胞外に放出されるメカニズムが重要であることが最近当研究室から動物モデルを使って発表されましたが、これがアルツハイマー病患者から単離されたエキソソームでも再現されるかどうかを検討中です。 他には脳内で近年注目を浴びている免疫細胞であるミクログリアがどのようにこの病理像の広がりに関与するかも検討中です。ゲノムワイド関連解析で発見されたアルツハイマー病と関連する遺伝子には複数免疫細胞、特にミクログリアを含めた貪食細胞の機能に関連するものがあり、これらのアルツハイマー病に関連する変異体遺伝子がどのようにミクログリアの機能に影響するか、創薬のターゲットになりうるかも研究中です。
2.米国で研究を始められた経緯についてお聞かせください。
私の米国生活の振り出しは24年前にUCSFの免疫学教室に短期研究留学をしたところからです。当時は東大病院での初期研修後で、大学院に入る前でしたので、まだまだ未熟でしたが、最先端の研究を現場で見られて非常に刺激になりました。2年後に米国で本格的に研究できる機会を戴き、MGHで3年間殆ど休む時間もなく研究に没頭しました。その後クリーブランドでポスドク、ネブラスカ州立大学で助教授から教授までを歴任した後、6年前にボストン大学に教授として招聘していただきました。
私の経験では研究人口、学生人口、大学の数と規模、製薬会社やバイオ工学会社、人種の多様性など総合してボストンが米国で外国人にとって最も研究に適した環境かと思います。
3.米国での研究生活についてお聞かせください。
良いところは世界の最先端の知識や技術がリアルタイムで入ってくるところです。特にボストンではほぼどの研究分野でも世界的な研究者が揃っており、共同研究やコンサルトの活用などでは非常に有利です。これは最先端の研究を常に進める上では必須かと思います。
悪いところとしては、研究環境は非常に競合的で、常に学会や発表された論文をチェックして仕事を出し抜かれないようにしなければならないことです。これはかなりの精神的肉体的なストレスとなりかねず、常に心身ともに健康を維持する必要があります。
4.日米の科学研究環境を比較して、日本の研究環境についてご意見をお聞かせください。
私の場合殆ど研究は米国で体験したため、日米の科学研究環境を正確に比較する立場にはありません。しかしながら、間接的な話としては、私が留学してくる前の日本の研究環境は米国とは比較になりませんでした。研究予算、研究施設、動物実験や安全性を管理するプロトコールや委員会の不備、ポスドク制度の不備、ポスドク後のポストの不備など、その違いは多岐にわたっていました。現在も中央の大学や研究所は研究環境が最先端レベルかもしれませんが、地方大学まで充実するには一層の資金援助と人的努力が必要なのではないでしょうか。
米国には寄付の文化があり、地方大学などの研究施設費用などは寄付によって賄われています。また、患者を含めた民間団体が活動費や研究費などの資金集めや議会への働きかけ、研究費の交付を行うなどの草の根的な活動が活発に行われています。 ただし、日本の良い点としては、他の研究者が御指摘のように雇用が安定していること、雇用者の給与を科研費から調達する必要がないことです。米国では研究者が自分の給与の殆どを科研費から調達する必要があり、これが非常に競合的な研究環境を生み出す原因でもあります。
5.日本の科学をさらに発展させるためのご意見があればお聞かせください。
日本の医学研修制度と大学院制度、ポスドクについて。日本のとりわけMDの臨床実学志向、収入重視傾向は、研究することの重要性と喜びなどに無関心な臨床医の量産に繋がっており、その結果が日本からの医師留学生の激減に繋がっているものと思います。 米国では医師の研究 離れをPhDが補い、これらを統括する指導者としてMD,PhDコース出身者を養成しています。日本でも同様の医師の研究離れが起こっているものの、医学研究へのPhDの参入や MD,PhDコースという養成プログラムがまだ一般的でないことから、将来の医学研究および医学教育指導者の枯渇を強く危惧します。
他には臨床応用と基礎研究のバランスを維持するために、研究者からのニーズをうまく取り込んだポリシーを明確にした科研費の公募を増やすことも重要です。そのためには、ポリシーを創案する専門職の雇用が必要かと思います。これは将来PhDを取得した人の別のキャリアとして米国では勧められています。
6.これから留学を考えている研究者にアドバイスがあればお聞かせください。
私の場合は所属研究室の教授の移動に伴い博士課程から米国で研究を始め、日本で地盤を作ることなく米国で研究を始めてそのまま研究を続けざるを得ない状況になり、自分の好きな研究に没頭することでここまで研究を続けることができました。
米国の研究環境は非常に競合的です。したがって、米国で生き残ることを目的にして研究をすることはおすすめ出来ません。できれば日本で博士課程を修了して地盤を作った後、米国に来られることをおすすめします。
7.ご自身の研究の将来展望や夢をお聞かせください。
今後当研究室の基礎研究が創薬開発と臨床応用につながることを期待します。具体的には病原蛋白の拡散のメカニズムを同定し、それを抑制する試薬をスクーリングするシステムを開発し、選択された治験薬を動物モデルや臨床実験で検定することを考えています。これには緊密な産学提携が必要であり、米国や日本など国家の枠を超えて自分の与えられた環境を最大限に活用して目標に近づけるよう今後も努力するつもりです。
【池津先生ご略歴】
- 1991年 東京大学医学部医学科卒業
- 1997年 同大学医学系研究科博士課程卒業
- マサチューセッツ総合病院及びクリーブランドクリニック研究員を経て
- 1999年 ネブラスカ州立大学医学部病理学科助教授
- 2010年 ボストン大学医学部薬理学科教授
ボストン大学池津研究室HP: http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/research/laboratories/lmnt/