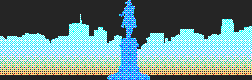東日本大震災被災地医療支援報告会を開催(7月11日)
東日本大震災被災地医療支援報告会を開催(7月11日)
東日本大震災被災地医療支援報告会を開催(7月11日)
このたび当館では、医療を中心とする東日本大震災被災地支援及びネットワーク作りを行うために当地在住の日本人医師及び公衆衛生の専門家により創設された「Boston-Japan Medical Relief Initiative 」(BJMRI:ボストン医療支援団)の活動報告会を総領事公邸で開催しました。
冒頭,参加者全員で黙祷を行った後,引原総領事から、東日本大震災後すみやかに支援活動を開始したBJMRI関係者に感謝の意を示すとともに、政府としても復興に向けて全力を挙げて取り組んでおり、医療や公衆衛生の分野では長期的な取り組みが必要でありBJMRIの一層の活躍を期待したい旨の挨拶を行いました。
続いて、5名の医師による活動報告が行われました。概要は以下の通りです。
1.ベスイスラエル病院/ハーバードメディカルスクール 橋本陶子医師(BJMRI代表)
「BJMRI活動概要」
震災直後、海外で研究活動を行っている自分たちのような者(日本の医師免許を有し、比較的日程が自由になる医師)が役立つ道が無いかと考えた。総領事館による支援や、資金提供者、多くの協力者を得て、日本への医師派遣を行うことが出来た。これまでに、10チーム、のべ14名の医師を日本に派遣した。3月11日の段階では今日集まった殆どの方と面識が無かったが、今次緊急事態にあたって多くの方の気持ちが一つになり、医師だけでなく法律、会計、ロジスティックスなどの専門家の力を結集してBJMRIが結成され、運営を行うことができた。
2.CMVコンサルティング 代表 出雲正剛医師
「福島再訪報告」
ボストンに来て30年になるが、このように医師が結集したことは初めて。自分は4月と6月の2度にわたり福島県の被災地を訪問。現地では心のケアを含めて長期的な対応の必要性を実感。大震災の教訓として、医療機関の所有するカルテ等の情報消失の可能性に備えるため、各個人が母子手帳のような自分自身の医療記録を所持する必要性を感じた。また、放射能については、リスクが過小評価されている可能性もあり、最悪の事態を想定した対応が必要。
3.ボストン小児病院/ハーバードメディカルスクール 崔明順医師(小児科医)
「石巻における医療支援」
5月下旬に国際医療ボランティア団体ジャパンハートの一員として宮城県石巻市の避難所等にて医療支援を実施。自身が福島県出身でもあり、放射能のリスクに関する対応と被災者へ可能な限り正確な情報を提供する必要性を実感。
4.ブリガム・アンド・ウイメンズ病院/ハーバードメディカルスクール 細川大雅医師(精神科医)
「被災者に真に必要な医療支援とは」
4月に4週間にわたり宮城県石巻市及び東松島市で医療支援を実施。精神科医という専門性を生かし、緊急医療活動に加え、地元自治体と協力して地域のメンタルヘルス対応体制の構築も支援。
5.ベスイスラエル病院/ハーバード公衆衛生大学院 津川友介医師(BJMRI副代表)
「公衆衛生の観点からの震災復興」
6月中旬から約3週間にわたり東北大学公衆衛生学講座に在籍し、厚生労働省の要請で東北大学地域医療支援センターが実施した被災者の健康診査に協力。
その後、BJMRIアドバイザーであるハーバードメディカルスクールのラッセル・フィリップス教授からの総括コメントに引き続き、参加者相互の懇親、意見交換が行われました。
BJMRIの活動概要や、被災地での医療支援にご関心のある方は、以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.bjmri.org/jpn
会場全景(総領事開会挨拶)

BJMRI代表(橋本医師)による活動報告
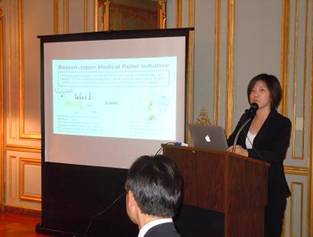
BJMRIアドバイザー(フィリップス教授)によるコメント
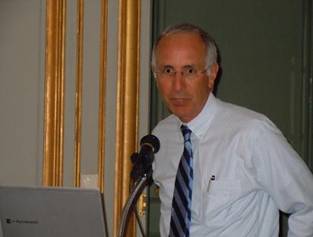
(2012/1/19)